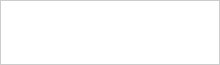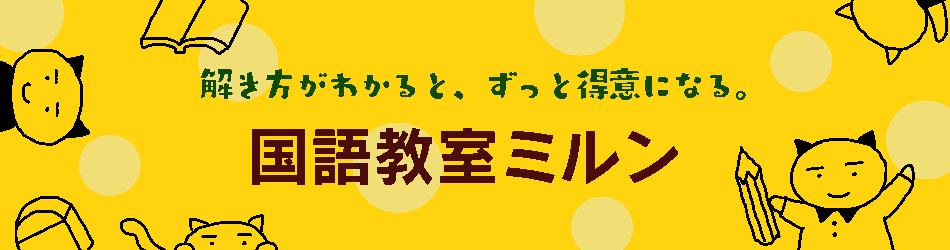子どもが文章を理解できない要因として、大きく分けて以下の6つの要素が考えられます。
①語彙力不足
②論理力不足
③読解力不足
④背景知識の不足
⑤注意力や集中力の不足
⑥読書量の不足
どれもがあらゆる学習の場で指摘されているものなので、聞き飽きたとは思いますが…
突き詰めるとやはりこれらが要因です。
今回は、それぞれの要因の
・特徴
・対処法
・おすすめのアプローチ
をまとめたので、ぜひ参考にしてください。
⸻
① 語彙力不足
知らない言葉が多いと、文全体の意味をつかめない。
例:「彼は気が進まない様子だった」→「気が進まない」が分からないと、内容が曖昧になる。
特徴:
・知らない言葉が多く、文の意味を一部しか理解できない
・ 「それってどういう意味?」とよく質問する(質問しないよりはまし)
・同じ言葉を繰り返し間違える・使い方を知らない
・慣用句、四字熟語、ことわざを知らない
・ 抽象語(例:誠実・二項対立など)に弱い
対処法:
・ミルンの【語彙力アップコース】を受講して、日常的に言葉を覚えることを習慣にする
・言葉を一気に覚えることは困難なので、コツコツ身につける習慣が必要
・家庭で自主的に語彙力を伸ばす工夫をする
・日常的に「語彙クイズ」や「言いかえ練習」を取り入れる
・読んだ文の中から「知らない言葉探し」をし、意味を理解する習慣をつける
・絵や体験とセットで語彙を定着させる(例:「しゃくり上げる」を演じてみる)
⸻
② 論理力不足
主語と述語の対応、接続詞や指示語を正しくたどれないため、文のつながりが見えなくなる。
複雑な文(二重否定など)も理解が困難。記述が苦手。
特徴:
・主語と述語の関係がつかめていない(変な文を書いても本人は気づいていない)
・一文が長くなると言葉のつながりが理解できず、内容が分からなくなる
・指示語(それ・このように・あれなど)が何を指すか分からないまま読み進める
・接続詞(しかし・つまり・なぜなら など)問題を間違える
対処法:
・ミルンの【通年クラス】で論理力を身につける
⸻
③読解力不足(未習得)
読解のルールを知らないため「どう読むのか」を意識せずに読む。
その結果、情報を取捨選択(整理)できず、字面を追うだけになる。
本人は内容を理解していなくても読んだつもりになっている。
特徴:
・何を意識して読めばいいのか分かっていない(読み方が雑)
・読むこと自体が作業になって、理解しようとは思っていない
・記述問題で何を書けばよいか分からず手が止まる
・読みながら「重要そうなところ」を選べず、 「この文の大事な部分は?」と聞いても答えられない
・問題を読んでも「何を答えればいいか分からない」ため、答えが的外れ
・論理関係(因果・対比・言い換えなど)が整理できない
・筆者の考えと自分の考えを混同しやすい
対処法:
・ミルンの【通年クラス】で読解法(ラインマークとフレームワーク)を身につける
⸻
④背景知識の不足
書かれている内容に関連する経験や知識が少ないと、イメージが湧かず理解できない。
特徴:
・「民主主義」「裁判」「戦争」など、身近でない話題は理解しにくい
・時代物、職業、制度、専門用語が多いとイメージできない
・想像することが苦手で、絵や図がないとピンとこない
・ 「このとき、どんな場面?」と聞くと答えに詰まる
・話を現実の経験と結びつけて考えるのが難しい
・特に小5以降、普段に比べて驚くほど低い偏差値をとることがある子は、このタイプに当てはまることが多い
→自分の知らない話題は理解できず、正答できないが、他の力(語彙力・論理力など)は不足していないため、精神的に成熟し知識が増えれば読める文章も増えてくる
対処法:
・前提知識を「図解」や「映像」で補う
・経験のある話題(身近なもの)で理解を促す
・「この場面、どんな様子だと思う?」など、想像力を促す質問を入れる
⸻
⑤注意力や集中力の不足(非認知能力)
一文一文の読み飛ばしや、途中で気が散ることにより、文脈のつながりを追えなくなる。
特徴:
・読んでいる途中でぼーっとする、気が散る
・文章の細部を見逃し、ざっくりとしか読まない
・音読すると飛ばし読みや読み間違いが多い
・問題文を最後まで読まずに質問に答えてしまう
・書いてあることを「見た気がするけど覚えていない」と言う
対処法:
・音読を活用し、「どこでつまずいたか」を確認する
・一段落ごとに区切って、要点を確認する
・読む前に「○○を探しながら読もう」と目的を示す
⸻
⑥読書量の不足(音読・黙読の習慣の欠如)
読書経験が少ない子は、読むスピードが遅い・理解が浅い傾向がある。
語彙や文のパターンに慣れていないため、スムーズに読めない。
特徴:
・読むスピードが遅い
・テストで時間内に最後まで解けない・一部しか読めない
・読むことを面倒に感じている
・読書が嫌い、または読書習慣がない
・本を読んでも内容をすぐ忘れる・話せない
・長い文・文章問題を見るだけで「無理」と言う
・勉強している割には語彙も読解スキルも伸びにくい
対処法:
・とにかく縦書きの活字を読むことに慣れさせる
・短くておもしろい読み物から入り、読書のハードルを下げる
・毎日5分でも音読の時間を作り、親や家庭教師が付き合う
・「読み聞かせ」や「読後の感想シェア」をする
⸻
まとめ:タイプに応じたアプローチが大切!
お子さんが文章をうまく理解できないとき、その原因は単に「国語が苦手」という一言では片づけられません。
語彙、論理、読解法、知識、集中力、読書量――それぞれ異なる要因が関わっています。
どこにつまずいているかは、お子さんによって違います。
今のお子さんに当てはまる特徴が多い項目こそ、今取り組むべき課題です。
まずはお子さんのタイプを見極め、今の課題に合った支援をしていくことが、確実な成長につながります。
⸻
各タイプへのおすすめアプローチ
①【語彙力不足】→ 語彙力アップコースで着実に強化
知らない言葉を減らすことが、理解力アップへの第一歩です。
②【論理力不足】③【読解力不測】
→ 通年クラスで読み方のルールを習得
「どう読めばいいか」が分かれば、読解はぐんと楽になります。
④【背景知識の不足】→ 図解・映像・経験で補いながら理解をサポート
知識が増えれば、読める文章も増えていきます。
ミルンの授業で文章を深く理解する体験も役立ちます。
⑤【注意力・集中力の不足】→ 読み方の工夫や声がけが有効
読み方を区切ったり、音読を活用することで、集中しやすくなります。
ミルンのライブ授業は、ぼんやりする暇がないテンポの良い授業です。
⑥【読書量の不足】→ 楽しく読める読書体験を積む
読書習慣をつけることで、読むスピードも速くなり理解力も育ちます。
家庭で本を読むことが難しくても、ミルンで文章を読むことが読書体験を担います。
⸻
国語教室ミルンの対応内容
⚫L1・L2クラス(年長〜小3)
→【①語彙】【②論理】【③読解】【④背景知識】【⑤集中力】にバランスよく配慮した授業設計です。
⚫L3〜L5クラス(小2〜小6)
→【②論理力】【③読解力】を中心に、【④背景知識】も補いながら、【⑤集中力】を保つ工夫をしています。
⚫L6〜L8クラス(小5〜中高生)
→【①語彙力】【②論理力】がある程度身についている子を対象に、【③読解力】+【記述力】の育成に重点を置いています。